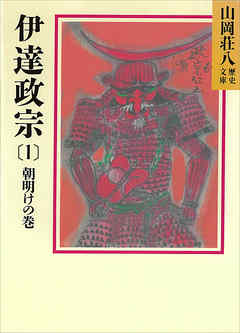歴史研究家・乃至政彦氏がテーマにゆかりのある古典を紹介するシリーズ。第3回は、天正13年(1585)10月8日に起きた「粟之巣の変」をテーマに、小説やドラマによって決定づけられた政宗像に迫ります!

父の死とともに修羅の道へと踏み出した政宗
天正13年(1585)10月8日、奥州の伊達政宗が粟之巣にかけつけると、二本松義継の手勢があった。その数23騎。
伊達家に追い詰められていた義継は、今後の関係を考え直してもらうため、政宗の父・輝宗と会見にやってきた。だが、義継は歓待した輝宗を強引に拉致すると、そのまま連れ去ろうとしたのだ。
鷹狩りを楽しんでいた政宗のもとに、火急の知らせが届いた。慌てて義継のあとを追う政宗。追っ手を恐れて振り返る暇も惜しんで居城を目指す義継一向。そして、ついに政宗はその姿を目にした。
──むざと父を連れ帰らせはせぬ
このとき政宗は戦慄すべき決断をくだした。なんと父のいる敵勢めがけて、鉄炮を撃ちかけさせたのである。銃弾を浴びて、ばたばたと斃れていく義継勢。憤怒の銃撃が繰り返された。あたりが硝煙に覆われるころ、義継たちの気配は消えていた。静寂のなか、敵の様子を確かめに足を進める政宗。そこには確かに義継と23騎の死骸があった。だが、そこには輝宗の亡骸もあった。これを「粟之巣の変」という。政宗は父の死とともに修羅の道へと足を踏み出したのだった。
物語の「粟之巣の変」

(東福寺塔中霊源院蔵)
政宗はすでに19歳のときに父から家督を譲られていた。若くして伊達家の選択を自ら定める権限が与えられていたのだ。だがそれは、重大な責任はすべておのれに帰する覚悟が求められる立場でもあった。
輝宗の死について責を問うとすれば、第一に輝宗や義継の名が挙げられよう。だが第二には政宗が指さされることになる。そこには是非も否応もない。その悲劇性はとても根深い。ゆえに「粟之巣の変」はドラマや小説で、政宗の決断力を物語る挿話として、常に大きな見せ場とされている。

(仙台市博物館蔵)
もっとも印象的に描いた「独眼竜政宗」
さて、この場面をもっとも印象強く描いたのは、大河ドラマ「独眼竜政宗」(第12回「輝宗無残」)である。ドラマでは輝宗が政宗に銃撃を促し、決断を迫る。変後、輝宗の亡骸を前にしていつになく嘆き悲しむ政宗の姿に涙した人は多いはずだ。
しかし、その原作である山岡荘八の『伊達政宗』はすこし様子が異なっており、苦渋の決断をくだしたのは、政宗ではなく伊達成実となっている。
声に出して読みたい山岡荘八『伊達政宗』
ところで山岡の文章は、名調子の響きが連なっていて、どちらかというと音読みに適している。ひとつひとつの文章じたいは文学的な渋みに乏しいが、大長編にはこの方が読みやすい。読んでいて疲れないのだ。ここですこし引用するので、声に出して読んでもらいたい。
「藤五郎、ここだ。輝宗はここにおるぞ。ここへもう一発、鉄砲を射ちこむのだ」
「それはなりませぬ! 月明りでは、大殿と義継の区別はつかぬ。過って大殿を射つやも知れませぬ」
「たわけめ! わしを生かして二本松へ送り込んだらどうなると思うのだ。わしの躰もろとも義継めを射ち抜くのだ」
成実は「あー」と短く何か叫んだ。もうこの時には半裸に近い姿で、成実は敵の中へ斬込んでいたのだ。
「歩けッ。歩かぬと刺し殺すぞ」
「藤五郎、わかったのかッ」
成実から返事はなかった。すでに乱戦になっている。と、何処から射ちだしたのか二発目の銃声が松並木の底でこだました。
「ウーム」
一瞬重なりあった輝宗と義継の動きが止まった。義継の白刃は輝宗の背から胸へ抜けていたし、銃弾は輝宗の胸をとおって義継の心臓を貫通してしまっていた。
(山岡荘八『伊達政宗』より)
本当に声に出して読んだなら、あなたは今の世に珍しい伊達者である。山岡の筆跡は長くても読み疲れしないものであることがよく理解されたはずだ。この特徴が古典の位置を占めるゆえんであろう。
史実の「粟之巣の変」
銃撃を命じた人物は史実では不明である。
同時代史料で同事件に触れたものは見られず、あとになって書かれた証言や回顧しか残されていない。しかも、それぞれ語り手や書き手の見聞きした話が異なるらしく、文献によって内容に違いがある。
命令もなく兵が勝手に動き出した説
たとえば、政宗の言行録としてしられる「木村宇右衛門覚書」には、輝宗が政宗に「しからば無念の次第なり、我をば棄てよ」と叫ぶように伝え、決断を促したとされている。ところが伊達成実の一代記『成実記』では、銃撃は特に誰からの命令もなく兵が勝手に開始したものだとされている。こちらのほうが政宗を擁護する色がうすい。政宗は輝宗の事故死を制止できなかったことになるからである。したがって両説を比較すると、前者より後者が信用できそうである。
鉄炮を武装する軍隊は、一般兵が命令に先行して、勝手に戦闘行為に入ってしまうことがある。昭和12年(1937)の盧溝橋事件は有名な例だろう。現場の兵は眼前の脅威を過度に恐れて、許可なく発砲することがしばしば存在したのである。このため、指揮官は行軍時の最前列に鉄炮ではなく、旗を立てさせる場合もあった。鉄砲を二番手に置くことで不慮の事故を避けようとしたのである。
義継勢の手による刺殺説
政宗を主人公とする近年の娯楽作品では、輝宗の死を政宗勢の銃弾によるものとする設定が大勢を占めている。だが、歴史資料では、義継勢の手による刺殺とするものが多いという。
もちろん事実は詳らかではない。まず二本松義継と会見した伊達輝宗が拉致された。それが鷹狩りを楽しんでいた政宗のもとに伝わって、駆けつけた。義継以下50騎は、政宗と交戦して、全員討ち死にすることになった。このとき輝宗も横死した。
以上の史実に複数の証言と後付けの物語が合わさって今日の「粟之巣の変」像が完成したわけである。
こちらも不明な「大坂夏の陣」
ところで政宗の敵味方問わない銃撃といえば、このほかにも「粟之巣の変」から30年後となる慶長20年(1615)「大坂夏の陣」で起きた「道明寺の味方撃ち」がある。
道明寺の戦いで徳川方の伊達政宗は、大阪方の後藤又兵衛勢と交戦した。このとき、先鋒の片倉重長の鉄炮隊により、銃撃戦を展開した。激しい戦闘の末、又兵衛は戦死する。政宗は夏の陣の緒戦で多大な武功を挙げたのだ。ところが「諸大名」はその働きを褒めるどころか「笑い物」にしたという。その理由は政宗が敵味方お構いなく銃撃したことにあった。
被害に遭ったのは大和国衆の神保長三郎。神保は政宗と同じく徳川方の水野隊に属していたが、後ろから政宗の銃撃を喰らったのだ。270人いた神保勢は、政宗の銃撃でわずか7騎のみにまで減った(『旧記雑録』)。非難された政宗は「神保が崩れかかったので、共崩れを避けるためだ」と弁解したといわれている。これ以外にも、政宗が苦労して戦果拡大の機会を作ったにも関わらず、神保が武功を横取りしようとしたので、抗議の意をこめて銃撃したとする記録も残されている。これも輝宗の銃撃同様、真相は不明である。
しかし、政宗はただ粗暴なる非情の人ではない。輝宗横死の一年ほど前、政宗傅役の片倉小十郎は誕生間近の自分の子供を殺そうとした。理由は定かでないが、これを聞いた政宗は翻意をうながし、「私に任せておいてくれ」「これをおし殺せば、わしはそなたを恨むぞ」と小十郎の自分に対する忠義を盾にしてまで、必至の説得を試みている(『伊達政宗文書』)。

(仙台市博物館蔵)
そのいっぽうで、政宗は子の忠宗に「御家の大事の前なら親をも見捨てる覚悟が大切だ」と述べていて(参考文献:佐藤憲一『伊達政宗の手紙』洋泉社MC新書、2010)、また先述の助命で生まれた小十郎の息子には「命には親の首をさえ斬ることもあるのだ。だから(無理な主命も)言うことを聞いてもらいたい」と懇請する手紙を送った記録が伝わっている(『片倉代々記』)。
悲劇を喜劇に塗り替える豪胆さ
政宗が輝宗を失ったとき、悲劇の主人公を気取ったというような記録は一切伝わっていない。だが、親を失う哀しみや苦しさを知っているからこそ上の発言には重みがある。政宗は自己主張の強い野心的な男だったが、自身の苦悩をベラベラ喋ったり、弱々しい言い訳をしたりするような軽薄な男ではなかった。
むしろ、すべての悲劇を喜劇のように痛快に塗り替えていく豪胆さがあるから、政宗にどのような逸話が残されていようと(創られようと)その魅力は微塵も色あせないのである。山岡荘八の政宗像が広く受け入れられているのは、山岡がその身勝手ながらも薄暗いところのない爽やかな可笑しみ──それこそ政宗根本の魅力である──を知り抜いているからこそだろう。
われわれの知る伊達政宗は、御涙頂戴を嫌っている。小さなことで泣いたり、くよくよしたりしてはいけない。無理な強がりもない。父の死も味方撃ちも「おれがわざとやったことだ。なにかわるいか」と心にも思っていないことで、小首を傾げて居直ってしまう。伊達者のなかの伊達者、それを決定づけたのが山岡荘八の『伊達政宗』である。
乃至政彦(ないし・まさひこ)
歴史研究家。単著に『上杉謙信の夢と野望』(ベストセラーズ、2017)、『戦国の陣形』(講談社現代新書、2016)、『戦国武将と男色』(洋泉社歴史新書y、2013)、歴史作家・伊東潤との共著に『関東戦国史と御館の乱』(洋泉社歴史新書y、2011)。監修に『別冊歴史REAL 図解!戦国の陣形』(洋泉社、2016)。テレビ出演『歴史秘話ヒストリア』『英雄たちの選択』など。
関連記事
【 古典を愉しむ 】第2回:通説の謙信像をアップデートした『天と地と』
【 古典を愉しむ 】第1回:名作!『関ヶ原』
【 上杉家の家督争い 】御館の乱と景勝の覚悟